
寿司の摂取による食後血糖への影響について
 研究の目的
研究の目的
食後の血糖値が急上昇し、その後急降下することを血糖値スパイクといいます。血糖値が急激に変動すると、活性酸素が大量に発生され、血管内が傷つき、動脈硬化が起こると言われています。血糖値スパイクを予防するためには「食事」が大事になります。これまで牛丼やサラダの摂取による食後の血糖値に与える影響についてご紹介してまいりました。今回は、和食の代表として世界中で知られている「寿司」に焦点をあて、その摂取が食後の血糖値にどのような影響を受けるのか調べてみました。
 実験方法
実験方法
18~25歳の健常な男女30名(男性:16名、女性:14名)を対象に、はま寿司の①寿司12貫、②すし飯のみ12貫、を食べてもらい、食後の血糖値を測定しました。また、すし飯の量が半分になった半シャリ寿司12貫を用いて、寿司種(ネタ)とすし飯の食べる順番による食後血糖値に与える影響について測定しました。

食事の前後で血糖値を測定しました(計7回)。

 実験結果
実験結果

※血糖上昇曲線下面積 (Area Under the Curve AUC)
時間経過に伴う血糖値増加量の面積で、食品摂取による血糖値上昇を比較する指標として用いられています。
※p<0.05/p<0.01 …統計学的に有意な差があることを示しています。
血糖上昇曲線下面積 n=30, mean±s.d.One-way ANOVA and Tukey’s HSD test (*p<0.05, **p<0.01)
寿司は、ただすし飯(白米)のみを食べるよりも血糖値の上昇が緩やかになる食事として
期待されます。糖質が気になる方でも、選び方・食べ方次第で楽しめる和食です。
期待されます。糖質が気になる方でも、選び方・食べ方次第で楽しめる和食です。
※この研究の結果は、日本食品科学工学会
第72回大会で発表しました
第72回大会で発表しました

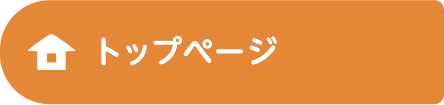
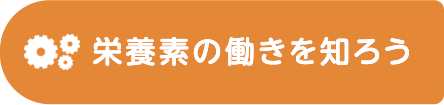

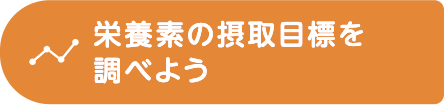


京都大学大学院農学研究科
教授 林由佳子先生のコメント
しかし、日本食ではおかずとご飯を一緒に食べることが多く、寿司やどんぶり、カレーライスはご飯を一緒に食べることを前提としています。果たして、血糖値のコントロールのために寿司のネタだけを先に食べてシャリを後で食べないといけないのでしょうか?今回の実験の結果、答えは「寿司は寿司の形で食べて良し」でした。もう目の前の寿司のネタとシャリを分解することはありません。そのままおいしくいただきましょう。